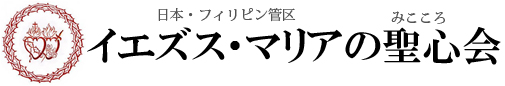「死者の月」に想う
〔そのとき〕復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か近寄って来て、イエスに尋ねた。
《「先生、モーセはわたしたちのために書いています。『ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の跡継ぎをもうけねばならない』と。ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女はだれの妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。」》
イエスは言われた。「この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも嫁ぐこともない。この人たちは、もはや死ぬことがない。天使に等しい者であり、復活にあずかる者として、神の子だからである。死者が復活することは、モーセも『柴』の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は、神によって生きているからである。」
ルカ20.27-38
【福音の小窓】
秋の深まりが日一日と色濃く感じられる季節となりました。晩秋の11月をカトリック教会では「死者の月」と呼び、亡くなった家族や親族。そして親しかった友人のために祈りを捧げます。そんな「死者の月」こそ、誰にでも必ずいつかは訪れる死について思いを馳せるには、ふさわしい時なのでしょう。
野に咲く草や花、風になびく樹々、空を飛ぶ鳥、野山を駆ける動物たち・・・生きとし生けるものすべてに終わりがあるように、人にも死という終焉の時があります。でも私たちは日々の生活の忙しさ、あわただしさに追われ、自分の死について思いを巡らすことはまれにしかありません。しかし、いくら束の間忘れ去っていようとも、死は私たち一人ひとりに確かな足音をもって、そして誰一人として例外なく忍び寄ってくるのです。
死とはなんでしょうか。人間の死とはいったいなんでしょうか。肉体と霊魂の破滅でしょうか。生きていた人間が無へと帰っていくことでしょうか。それともただ謎なのでしょうか。
死を体験したことのない私たちは、経験から死を語ることはできません。しかしキリストを信じる私たちは、キリストの言葉から死の神秘を解き明かす術を知っています。
キリストによれば、死とは復活する日までの仮の住まいの場なのです。人は皆新しい命へと復活するために、死という暗く悲しい闇を通らなければならないのです。
生きている私たちは、親しい者の死を体験する時、そのあまりに辛く、悲しい闇の深さに、身を焼かれるほどの苦しみを味わわなければなりません。親しい者との別れほど、私たち人間にとって悲しいことはないからです。
しかしキリストを信じる者の死は、何も見えぬ真っ暗な中の悲しみではありません。死の彼方に悲しみの彼方に、一筋の光の見える悲しみです。
その光とは「復活の光」です。キリストが約束して下さった復活という光。私たちは死と言う暗闇を前にした時にでも、その一筋の光から目をそらしてはいけないのです。
亡くなった私たちの家族や親族、そして親しかった友は、今はまだ私たちが遥か彼方に小さく見えている光、その光を身体いっぱいに浴びて、温かな神の恵み、永遠の憩いの中で安らかに生きているに違いないのです。
親しい者の死を体験した者の涙は、すぐに乾くはずもなく、思い出せばまた悲しみが蘇ります。しかしカトリック教会が定める「死者の月」は、ただ悲しみの時ではありません。もう一度悲しみを呼び覚ます時でもありません。何よりも「死者の月」は、残された私たち一人ひとりが、自分の人生を精一杯生きていくことを誓う場です。なぜならそのことだけが、天の国に召された故人に私たちができるただ一つの捧げものだからです。
その生涯を、悲しみや苦しみを抱きながらも精一杯に生き抜いた私たちの家族や親族、そして親しかった友人に、イエスはこう言っているに違いありません
「友よ、来たれ我が元へ。休ませてあげよう、あなたは最後まで私の十字架を担ったのだから」。
イエズス・マリアの聖心会
本間研二