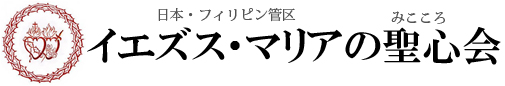ありのままの自分で信仰を伝えよう

さいたま教区「福音・宣教化年」茨城地区の取り組み
イエズス・マリアの聖心会
本間研二
はじめに
2016年の暮れ、教区管理者・岡田大司教は2017年を「さいたま教区 福音・宣教化年」とするとの宣言を出された。北関東四県がそれぞれに思案して「福音を宣べ伝えよ」とのことである。茨城地区に属する我々は、早速その旨を持ち帰り、準備に取りかかった。
まず地区の司祭の集まりであるIAC(茨城エリア・コミュニティー)に議題が出され、その後に使徒職協議会で話し合われたが、実のところ「福音・宣教化」と言う、教会にとっては最も重要であるはずの言葉に、誰一人として瞳を輝かせて反応する者はいなかった。興味がないむけではない。関心がないわけでもない。ただ新鮮さがないのだ。3年前も5年前も10年前も、もっともっと前から教会の中で「福音・宣教化」という言葉は叫ばれてきた。そしてその言葉に応えようと、信徒も司祭も、一人ひとりが必死になり、教区の枠で、そして小教区と言う現場で精いっぱい頑張ってきた。それでも今、目の前にあるのは信徒・修道者・司祭の高齢化、若者の減少と教会離れ、それに伴う教会の老衰化という、動かし難い現実である。
いったい今日の日本での「宣教」「福音化」とは何だろう。昔から繰り返し問われ続け、幾度となくその前で立ちつくしてきた高い壁のような問いではあるが、岡田大司教からの「福音・宣教化年」宣言を、その立ち尽くした壁への再チャレンジ命令と受け止め、茨城地区では、「日々の生活の中で、私たちが出来る福音宣教とは・・・」と言うテーマで取り組むこととなった。
以下、「宣教・福音化」に関わる私自身の経験を述べたうえで、地区の全体的な取り組みを紹介したい。
叙階直後のつまずき
神学校を卒業して小教区に派遣が決まり、胸躍らせながら着任したのは、もう30年近く前のことである。叙階式直前のミサで、当時の院長は「君たちは、これから司祭として教会に派遣されていくが、教会に着任した時から『神父様』と呼ばれる。でもいくら『さま、さま、さま』と呼ばれても偉くなったわけではないから、勘違いしてはいけない。」と訓示した。その言葉に胸を張って「ハイ」と答えて、勇ましく赴任教会へと向かったことを覚えている。しかし「ハイ」とは言ったものの、「自分は8年間も修道会と神学校で養成・教育を受けたのだから、多くの人に福音を伝えねば」という安っぽい自尊心と、必要以上の心の高ぶりがあったのだろう。神学校で培った知識 (聖書学や教会論など?) を教えることが宣教だと思い込みんでしまった。説教の準備のため、神学校での習いたてのノートや神学書を開いては、哲学や神学用語が散りばめられた文言を写し取り、ミサではその字面を目で追いながら朗読をした。中身がないのに背伸びをしていたのだ。
そんなある日曜日。ミサの後で一人のご婦人が私に言った「神父さまの説教はつまらない。どんなすばらしい説教でも、下を向いて原稿を読んでいるだけでは何も伝わってきません。それに私たちは、難しい神学や聖書学を学ぶためにミサに来ているのではなく、毎日の生活の中で、生きていく力と支えを求めて教会に来ているのです。だから神父さまの支えとなっている信仰を、神父さまの言葉でおっしゃってください。私たちを見て話して下さい。」と。
あのときは、心が折れるほどに痛く、しばらく落ち込んで立ち上がれなかったけれど、今にして思えば、福音を伝えるとは、自分の信じるものを自分の言葉で伝えることでもあるとわかる。己の心を開き、弱さや失敗や未熟さをもさらけ出しながら語るのでなければ、思いを他者に伝えることなど決してできることではないのだ。あのときの婦人の言葉は、かけがえのない励ましだったと、今は心から思う。
新庄教会での体験
司祭になり15年が過ぎた頃、私は山形教会で働いていた。そこから60キルほど内陸に入った最上郡という地域には、以前よりフィリピンからの「農村花嫁さん」たちが大勢やってきていた。彼女たちのために毎週ミサに行くのだが、当時教会はなく、公民館の会議室や食堂の大広間、ホテルのホールなど転々としながら、何とか細々とミサを続けていた。「でも、やはり自分たちの教会が欲しい」。そんな声が彼女たちの中で広がった。途方もない夢であったが、当時の菊地功司教の後押しと大勢の方々の励ましと力添えによって、少しずつ希望が現実へと近づき、ついには廃園になった幼稚園を買い取り、リニュアールして献堂されたのが新庄教会であった。この地域は全国屈指の豪雪地帯で新庄教会も冬には3メートルの雪で覆われる。周りは山々と田園に囲まれ、絵に描いたような田舎と言ってもよく、日本人の信徒は2人だけで、あとは全員フィリピン人の花嫁たちである。
山形教会でのミサがあるので新庄教会でのミサはいつも午後になる。私が着く頃には多くのフィリピン人たちが教会に集まり、母国の言葉でおしゃべりをしている。そんな中で私がしばしば目にしたのは、教会の近くの田んぼで農作業をしているじいちゃん、ばあちゃんと話し込んでいるフィリピン人たちの姿だった。私が最初に心配したのは、「教会の人間が馴れ馴れしく近所の人に話しかけたら警戒されはしまいか。”宗教の人”と迷惑がられはしまいか」ということだった。だが私の心配など無用だった。何の躊躇もなく飛び込んでいく彼女たちの明るさに、じいちゃんもばあちゃんも微笑みながら話し込み、ときには野菜などをもらって教会に帰ってくるのだ。それだけではない、時にはミサが終わった頃に数人のばあちゃんたちがお茶菓子を持って教会にやってきて、彼女たちと仲良くおしゃべりをしたり、彼女たちが誘われて、ばあちゃんたちの家に遊びに行くようなこともあった。
そんな姿を見て、これこそ「宣教」であり「福音化」ではないかと強く思った。彼女たちは聖書を振りかざして隣人と関わっているのではない。難しい神学も語ってはいない。でも彼女たちは紛れもない「宣教者」だった。聖書をもって司祭館にこもっている私たち司祭よりも、その姿は見事な「宣教師」であった。
ある時一人のフィリピン人に「あのばあちゃんと、どんな話をしていたの」と聞いたことがあった。彼女は「日本に来たとき、『冬は寒くて、家族とは遠く離れて寂しくて、結婚したけど、だんなと言葉が通じなくて、つらかったよ』って言ったら、ばあちゃんも私と一緒に泣いてくれたんだよ」と恥ずかしそうに話してくれた。心を開いて他者と関わる時、国籍も宗教も超えて共感が生まれる。それこそが「宣教」の土台でなければならない。紛れもなく彼女たちの中に、私たちが見習わなければならない「宣教者」の心がある。
現代の迫害
東北の片田舎で生まれ育った私が信者となったのは23歳の時だった。洗礼を受けてしばらくして、職場の同僚にポロリと自分がカトリックの信者であると告げた。同僚は怪訝な顔をして「えっ、お前、洗脳されたのか」と私の顔を覗き込んだ。職場ではその後、しばらく私のことが話題になったようだ。「本間は自分に自信がないから宗教に走ったんだ。」とか、「宗教に入ったなんて危ないやつだ」とか、「やっぱり変わっていたからな」などなど。私はそれからしばらく、職場では信仰について語ることはしなかった。地域差もあるだろうし、私が洗礼を受けた当時と今とでは、時代も違ってはきているだろうが、そのような風潮が今の日本の社会の中で皆無とは思わない。
確かに、400年前の禁教の時代や幕末・明治初期の浦上四番崩れのときのような肉体的な拷問や迫害はもはやない。他方、職場や学校など、社会の中で信仰を表明して生きようとしたときには、精神的な「迫害」を覚悟しなければならないのが今なお続く現実である。ミッションスクールやカトリック系の職場、または教会の中でならともかく、何ら宗教と関わりのない場で、自分の信仰を表明し生きることは難しい。
しかし勇気を持って自分の信仰を語り出したとき、私たちの前に立ちふさがる壁は、少しずつ崩れ落ちるような気がする。途方もなく地道に見える「私たちの福音宣言」こそが、実は日本の「福音・宣教化」への道なのだろう。
勉強会での敗北
いわゆる「上からの宣教」に燃えていた頃、中学生に聖書を教えていたことがあった。前もって聖書の解説書や文献を読み、レジュメを作り、授業の進め方や息抜きの冗談まで万端整え、私なりに頑張って準備をした。そんな涙ぐましい努力をしたにもかかわらず、最後の日に書いてもらった感想文では「神父さんの話し、難しくてよく分かりません」「黒板の字が汚くて読めなかった」「おやつがショボ過ぎ」とボロクソのありさま。つまり私の神学校での勉強も、教会で培った経験も、築き上げたものが、中学生の前ではまったく通用しなかったのだ。
しかし大聖人パウロも似たような体験をしたようだ。パウロは「わたしは生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です・・・」(フィリピ3.5)と誇らしげに語るように、その出自も学歴も当時のユダヤ人としては超一流のものだった。そんなパウロが誇っていたものを、イエスはいとも簡単に粉砕する。イエスはこんな風に言ったのかもしれない「パウロよ、お前の履歴も実績も素晴らしいのはわかる。でも私が求めるのはそれじゃないんだよ」と。イエスとの出会いはパウロに今までの自分との「決別」を求めるものだった。そして「決別」の決心をしたとき、パウロは一つの答えをもらう。「いいか、パウロ、人々はお前の知識や資格を欲しているのではない。ただ愛を欲しているのだ」と。これこそが「宣教の原点」なのであろう。
中学生たちが私に求めたのは、私の聖書の知識や解釈ではない。愛が欲しかったのだ。それに気づかない私は、ただ聖書の知識をひけらかし、感動させようと躍起になっていた。もしかしたら教会は、今も、持っている物をせっせと提供しているだけなのだろうか。
愛とはきっと、持っている物を提供することでも、感動させることでもない。自分の持っている物がすべて通用しないとわかったとき、今までの自分との「決別」の後にこそ輝き出すのだろう。
茨城地区の取り組み
それでは、さいたま教区の「福音・宣教化年」に話を戻そう。その実施に際しては、埼玉・栃木・群馬・茨城の4地区がそれぞれの場で、「自由にやってよし。そのためのお金は出す」というのが岡田大司教からのお達しであり、それに沿って4地区がそれぞれに実施することとなった。
茨城地区でも他の地区と同様、一年を通して聖書の勉強会・講習会を催してはどうかという意見が出た。しかし思うに、信徒の方々は長年にわたり、日々祈り、ゆるしの秘跡を受け、毎週ミサにあずかり、真摯に信仰を生きて来た方々である。その方々に、さらに勉強会や講習会の受講を求めるのは、「あなたがたは、もっともっと聖書の知識を身につけ、教会の掟を学ばなければ、福音を宣教する資格はないのだ」というメッセージを送ることになりはしまいか、そのようにハードルをむやみに上げることは、教会にとって決して有益なことではないのではないか。私たちはこう考え、これからさらに学ぶ知識ではなく、「今のままのあなたが宣教者です。勇気を持って自分の信仰を伝えよう」を旗印にして、カトリック水戸教会を会場に、信徒による信仰の「証」を発表する運びとなった。・・・とは言ったものの、カトリックの信徒は学ぶことには慣れているが、自らの信仰を発信する場所も機会もそれ程与えられてこなかったためか、呼びかけに進んで答えてくれる人はいなかった。そこで狙いを定めた人に粘り強くお願いしていくという、至って素朴な方法で発表者が選ばれていった。発表者は次のような方々である。
- 助産師を目指して学んでいる23歳の女性。
- 東日本大震災後から福島県いわきでボランティアをしてきた婦人。
- インドネシアから家族4人で来日され、日本の教会で信徒会長をされている男性。
- 海外出張の中でカトリックに出会い、その出会いから洗礼を受けた男性。
- プロテスタントからカトリックに改宗された男性。
この方々に発表を依頼するにあたりお願いしたことは、「自慢話やきれいごとでまとめるのはやめて下さい。恥ずかしいかもしれませんが、できれば人生や中での失敗や危機、または挫折の経験をお話しください。そしてそのときに信仰や教会は、あなたのとってどんな支え、励ましとなりましたか。また逆に、つらいときに教会が支えと感じられずに落胆したことはありましたか」ということだった。
どの発表者も教会での分かち合いや小グループでの発表はしたことがあっても、大人数の中での発表は初体験ということで、発表者も聴衆も緊張の中でのスタートだった。しかし、発表者全員がそれぞれに自分を深く見つめ、絶望や挫折をしたときに支えとなった信仰や教会、信徒や神父の存在について、また信仰への不信、教会への不満なども含め自らの現状を赤裸々に話してくださった。そんな話に聴衆のみんなが引き込まれ、ときには笑い、そしてときには涙しながら、自らの信仰と照らし合わせながら聞き入ったひとときではなかったかと思う。
今回の茨城地区の取り組みは、福音をただ「学ぶものから」、ありのままの自分で「信仰を伝えよう」という試みと言える。もしかしたら私たちは、自ら福音を宣べ伝えるためのハードルを高く掲げ過ぎてはいないだろうか。私たちが伝えようとしているのが学問上の神ではなく、イエスが指し示す神ならば、私たちはその神を飾らない素朴な心で素直に伝えればいい。ほんの少し勇気を持って私たちが語り出したならば、私たち一人ひとりは紛れもない現代の「宣教者」となれるのだ。